弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
個人破産の場合、目指すべきゴールは、「裁判所から免責許可の決定をもらう」になります。免責許可が確定した場合、借金の弁済義務が免除されることになります(破産法253条)。しかし、破産法は、裁判所が免責を認めない事項、いわゆる免責不許可事由を規定しており、その中に浪費・ギャンブルによる借金(破産法252条1項4号「浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」)があります。
では、浪費・ギャンブルによる借金は、破産手続きにおいて免責が認められないかというと、そうではありません。裁判所は、免責不許可事由に該当する場合であっても、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができ」ます(破産法252条2項)。いわゆる裁量免責です。
破産法は、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮」する旨を規定していますが、実際にどのような事項が重視されるのかは、裁判所の専権事項になります。
もっとも、多数の破産事件を扱うなかで、裁判所は下記の事項を重視しているのではないかと推察しましたので、ご紹介させていただきます。
借金のうち、ギャンブル等に消費された割合が重視される傾向にあると思います。借金の一部がギャンブルに消費されているが、殆どは生活費に消費した等の場合であれば、裁量免責が認められやすい傾向にあります。
裁判所は、破産を申し立てる人が生活等を改善することで、再度、破産をする可能性がなくなるか否かを見ています。もし、ギャンブルで多額の借金があるとしても、どのような原因でギャンブル等にお金を消費してしまい、返済不能に陥ったのか、また、どのように生活等を改善すれば、生活を再建することができるのかを検討し、具体的に裁判所へ報告することで、裁量免責が認められるケースが多いです。
裁判所が一番重視しているのは、本人が反省しているのか否かだと思います。どのように反省していることを裁判所へ伝えればいいのかは事案によりますが、すべての事案に共通する事項は、「正直であること」です。
破産手続きを進めるにあたり、裁判所に対し、多数の資料を提出する必要があります。例えば、保有している口座情報を隠したり、借金が増えた経緯をごまかしたり、嘘をついたりすると、それらが裁判所の調査によって発覚した場合、裁量免責を得ることは非常に難しくなります。弊所では、多数の破産事件を扱いましたが、最初から全て正直に回答している方であれば、免責不許可になった事案は今のところございません。
免責不許可事由に該当する可能性が高い事案では、裁判所から管財人が選任されることがほとんどです。管財人が選任された場合、管財人が裁量免責にするべきか否かの意見を裁判所へ報告するため、管財人の調査についても正直に対応する必要があります。
免責不許可事由があるからといって、破産ができないわけではありません。ただし、破産の申立てにあたり、「正直」であることが必要になります。破産を検討されている場合には、早期に専門家へご相談ください。
クレジットカード等の借入で首が回らなくなってしまった。住宅ローンの返済もある。 でもそんなときでも個人再生手続を使えば、債務の返済額を減らすことがきる。住宅資金特別条項を使えば、マイホームも残すことができる。個人再生は何と素晴らしい手続きか、マイホームがある場合は個人再生一択!!! ……と、飛びついてもよいのでしょうか。
個人再生手続終了後は、個人再生手続において減額した債務を、原則3年で返済しきることになります。その返済計画のことを、「再生計画」と言います。弁護士と契約を締結する前に、再生計画がどのようなものになるのかの見通しを立てて、再生計画どおりの弁済ができるかどうかを検討する必要があります。 ここにAさんという人物がいたとします。Aさんはマイホームを持っていますが、まだ住宅ローンの返済は終わっていません。住宅ローンを除いた債務総額が2500万円で、全てクレジットカード・消費者金融の借入です。ローンは月額8万円です。 Aさんは、どのような再生計画になるでしょうか。
個人再生においては、債務額が1500万円を超え3000万円以下の場合、弁済額は300万円になります(民事再生法231条2項4号)。 現時点で債務総額が2500万円だということは、個人再生手続申立てをする半年後には、遅延損害金が加わっていることになります。遅延損害金の利率は債権者によって異なりますが、仮に2割だとすると、半年で弁済しなければならない債務の額は2750万円になります。 いずれにせよ3000万円以下なので、弁済額は300万円となる可能性が高いでしょう。 また、個人再生の場合は、清算価値保障原則にも注意が必要ですが、これはAさんはクリアできているとします。
先述のとおり、原則3年で減額した債務を支払うことになるので、Aさんが月額の返済額は、8万3000円前後になります(3,000,000÷36=83333.333・・・)。 毎月遅滞なく不足なく支払うことが必要になるので、月額8万4000円は支払えるだけの余裕があった方が良いでしょう。 Aさんの再生計画は、月額8万3000円から8万4000円を支払うものになる可能性が高いと言えます。
Aさんが再生計画どおりの支払いができるかどうかの判断において非常に重要となるのは、家計の状況を把握することです。 Aさんのある月の家計の状況をまとめると、下記のようになりました。
| 収入 | 支出 |
|---|---|
| Aさんの給与(手取り) 200,000 |
住宅ローン 80,000 |
| 配偶者の給与(手取り) 100,000 |
光熱費 30,000 |
| 前月繰越 25,000 |
電話料金 30,000 |
| – – |
食費 40,000 |
| – – |
医療費 3,000 |
| – – |
被服費 5,000 |
| – – |
教育費(学費) 110,000 |
| – – |
交際費 5,000 |
| – – |
翌月繰越 22,000 |
| 収入合計 325,000 |
支出合計 325,000 |
当然ですが、このAさんの家計状況は完全なる創作です。
翌月の繰越が2万2000円しかありません。これでは、月額8万4000円の弁済を毎月していくのは難しいと言えます。 節約して減らせる出費があればよいのですが、住宅ローン代や教育費は毎月固定でかかるものであり、また食費を減らすことも現実的ではありません。 残念ながら、Aさんが個人再生手続をしても、再生計画どおりの弁済をすることは難しいと言わざるを得えません。
3年での弁済が難しいことを説明し、4年や5年での弁済とする計画を認めてもらえるよう裁判所に上申することもありますが、認められるかどうかは不明です。 また、Aさんの場合、4年の弁済でも月額6万2500円、5年の弁済でも月額5万円の弁済計画になりますので、結局難しいと言えます。
個人再生においては、再生計画案を申立人が提出し、債権者が多数決で可決するか否かを決議し、そのあとで、裁判所が再生計画案を認可します。しかし、再生計画が遂行される見込みがないときは、裁判所は再生計画不認可の決定をします(民事再生法174条2項2号)。 個人再生手続の申立てにおいて、裁判所には家計の状況を記載した書面を提出します。その書面に照らし、裁判所が、再生計画が遂行される見込みがあるかを判断した結果、見込みがないとされれば再生計画は不認可になってしまいます。そうすると、裁判官の判断次第では、破産開始手続決定がされることがあります。
再生計画が認可されても、再生計画どおりの弁済ができなくなり、結局破産を申立てることが必要になる可能性があります。
個人再生手続の申立てを弁護士に委任する前に、再生計画の見通しを立てておかなければ、再生計画が認可されても結局首が回らなくなり、破産を申立て、マイホームを手放さなくてはならなくなる可能性があります。 誰もが現状の生活を維持しつつ、債務の弁済額を減らすことができるわけではありません。計画どおりの弁済をすることが難しいのであれば、破産手続の検討をすることも必要です。
個人の方の破産(いわゆる自己破産)の手続における最終的な目的は、免責手続きにおいて、免責許可決定を受けることにあります。
免責許可決定が確定すると、破産者は、原則として債務の支払い義務を免れることができます。
しかし、破産法上、免責許可決定を受けても支払い義務がなくならない債務があります。
このような債務を「非免責債権」といいます。
非免責債権は、破産法の253条に規定があります。
以下では、それぞれの非免責債権について簡単に述べたいと思います。
① 租税等の請求権
名前のとおり、税金や、社会保険料等の債務です。
租税等については、通常の借り入れ等とは異なり、簡易に差し押さえが可能です。
長期間滞納し、給与の差し押さえをされてしまうと、破産の準備等に支障が出る可能性もありますので注意が必要です。
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
ここでいう「悪意」とは法律用語における悪意(ある事実について知っていること)では足りず、積極的に他者を害する意思(害意)が要求されるものと解されています。
例としては、会社から横領をした場合の返還義務等が考えられます。
③ 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
生命身体を害する不法行為については、通常の不法行為よりも賠償による救済の必要性が高いため、②よりも要件が緩やかに、故意または重過失によって生じた損害については、免責されないこととされています。
例としては、重過失によって生じた交通事故による損害賠償義務等が考えられます。
④ 次に掲げる義務に係る請求権
夫婦間、家族間の扶養義務については、要保護性が高いことから、免責許可決定によっても免責されません。
典型的なものは、婚姻費用、養育費です。
破産手続開始決定時における債権は、破産手続の対象となりますので、破産手続開始決定時に既に未払となっていた養育費等は、破産手続中は他の債権と平等の取り扱いを受けます。
しかし、免責はされませんので、破産手続終了後には支払う義務が残ります。
また、破産手続開始決定後に期限が到来する養育費等については、通常通り支払い義務が毎月発生します。
なお、破産手続開始決定前に調停等で養育費等の支払い義務が定められている場合、破産手続開始決定前の原因に基づく債務に該当し、他の債権と同様に扱わなければならないようにも思われますが、実際の支払いまで時間がかかってしまうという弊害がありますので、実務上はそのようには扱われないことが多いと思われます。
⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
労働者保護のための規定と考えられ、個人事業主の方が破産する場合の従業員の給料などがこれに当たります。
免責の対象となっていないため、従業員を雇っている個人事業主の方の破産においては、給料の支払いができるかどうかを検討する必要があるでしょう。
⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
破産者が、債務の存在を知りながら、その旨を申告せず、債権者名簿に記載されなかった結果、破産手続に参加できなかった場合、その債務も免責されません。
なお、債権者名簿に記載しなくても、破産手続のことを知っている債権者の債務については免責の対象となりますが、知りながら名簿に記載しないことがそもそも不正な行為として免責不許可事由となっています(破産法252条7号)。
そのため、把握している債権者については、非免責債権に該当することが明らかであっても、全て適切に申告する必要があります。
⑦ 罰金等の請求権
刑事上の罰金や科料、行政手続上の過料等が含まれます。
破産した場合であっても、自ら支払うべきものとされており、免責されません。
非免責債権は、免責不許可事由との関係はありません。
免責不許可事由は、免責を許可するかどうかという問題であるのに対し、非免責債権はそもそも免責の対象とはならない債権がどのようなものかという問題であるため、問題となる段階が異なるからです。
したがって、非免責債権があるから、免責を許可すべきでないということはありません。
そのため、非免責債権であることが間違いないような負債を抱えている方であっても、その前提で、他の借り入れなどの債務の免責を受けるために破産手続をするということもあり得ます。
また、破産手続においては、非免責債権に該当するかどうかが判断されることはありません。
非免責債権に該当するかどうかが問題となる例としては、債権者が、債務者に支払い等の請求をした場合において、債務者が免責によって支払い義務を負わないと反論し、これに対して非免責債権に該当するという再反論をするということが考えられます。
本稿では、非免責債権について概観しました。
弊所では、破産や債務整理のご相談をお受けしています。お困りの方は一度ご相談ください。
破産管財人は、破産申立人を本当に破産、免責してよいのかを調査するために、裁判所が選任する人物になります(破産法74条1項)。 管財人の選任は、裁判所の専権であるため、選任基準は不明ですが、岡崎支部ですと、破産申立人の住所地の近くに事務所を有する弁護士が選任される傾向にあります。
破産管財人は、破産者の財産を管理、処分する権利を有しており(破産法2条12項)、破産者の財産管理、換価、配当を行う権限があります(破産法78条1項)。 また、破産手続きにおいて重要となる残債務の支払い免除(免責許可決定)について、裁判所に意見を述べる立場にあります(破産法250条)。
このように、破産管財人には様々な権限があるとともに、破産手続きを行う上で、非常に重要な人物となります。
破産法上、破産管財人の業務を妨害することや、破産管財人に虚偽の事実を申告することは、免責不許可事由に該当します(破産法252条1項8号、9号)。免責とは、破産によって破産申立人の財産を換価、配当してもなお残債務が生じる場合に、残った債務の支払い義務を法律上免除する制度をいいます(破産法253条1項)。
つまり、破産管財人の指示に従わない場合、免責不許可となるおそれがあり、債務の支払い義務が免除されない可能性があります。
破産手続きを裁判所へ申立てすると、通常、約1か月程度で裁判所から破産開始決定がなされます。 その際、ほぼ同時に裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人選任後、破産申立人は、早期の段階で破産管財人と面談することになります。
面談の中で、どのように債務が増加したのか等の聞き取りが行われるとともに、今後の生活状況をどのように改善していくのか等の指導がなされます。 同面談は、約1か月に1回ほどの頻度で継続的に行われます。
破産申立後、破産申立人が1人で破産管財人の事務所へ赴き、今までの破産手続きの進捗等を破産管財人へ説明することは、かなりハードルが高いと思います。 そこで、弊所では、破産開始決定後、速やかに破産管財人へ連絡をとり、管財人面談の日程を調整します。
その際に、破産管財人へ現状の報告等を行うようにしています。また、初回の面談にも同席の上、当方から破産管財人に対し、破産手続きの進捗を説明するようにしています。
破産手続きは、必要書類を集め、裁判所へ破産手続きの申立てをしただけでは終わりません。 特に破産管財人が選任される場合は、管財人による調査への協力等、やるべきことが沢山あります。破産手続きを検討されている場合には、早期に専門家へご相談ください。
弁護士が破産手続開始申立を受任すると、破産手続開始申立を受任した旨を知らせる書面である、受任通知を債権者に送付します。弁護士による債権者への受任通知の送付は、支払停止(破産法15条2項)とみなされます(最判平成24年10月19日)。
支払停止とは、「弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できないことを表示する債務者の行為とそれに続く債務者の態度」とされます(大審院判決昭和15年9月28日参照)。
お給料日が来たら払えるというわけでもなく、ある債権者からの借入れだけを返済できないというわけでもなく、「みんなの債務をずっと弁済できない。」という状況にあることを表示する行為・態度です。
支払停止後は、いくつか注意が必要な点があります。
支払停止後に、特定の債権者にのみ弁済をすることは、偏波弁済として、否認権行使の対象になり(破産法162条1項)、結果的に支払ったお金を返してもらうことになる可能性があります。
返してもらうためには、支払いを受けた人が、債務者が支払不能であったこと又は支払の停止があったことを知っている必要があります(破産法162条1項1号イ)。
では、返してもらうことを防ぎ、支払いを続けたい債権者には受任通知を送付しなければいいのか、というと、そうでもありません。
破産の際は、破産者は債権者名簿を提出する必要があり、その債権者には破産者が把握しているすべての債権者を記載しなければ、虚偽の債権者名簿を提出したとして、免責不許可事由にあたります(破産法252条1項7号)。
免責とは、債務の責任を免れさせることで、債務者を返済義務から解放するものです。友人や親族からの借り入れも届けなければ、債務全体の免責がされない可能性があるのです。裁判所に破産債権者として届けるので、受任通知を送る必要があります。
支払停止後は、生活が苦しくなったとしても、借入れをしてはいけません。支払停止状態にあるのに、その事実を隠してお金を借りたとなれば免責不許可事由になるからです(破産法252条1項5号)。
お金を返せないのに借りることは、貸してくれる人に、返せるかのごとくだますことですので、免責不許可事由に該当します。
たとえ親しい人であっても、経済援助を受けるときは、借入れではなく贈与としなければなりません。
破産手続にのっとって債権者に弁済がされるのであれば、債権者平等の原則から、他の債権者の債務は免責し、特定の債権者の債務だけは全額弁済されるということは認められません。
親しい人からお金を借りている場合であっても、破産をするのであれば、他の債権者と同様、弁済をできなくなることになりますから、注意が必要です。
令和6年12月17日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について再生計画認可決定確定が出ました。
令和6年12月25日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について申立てました。
令和6年11月6日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。
令和6年11月28日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について破産手続廃止決定が出ました。
令和6年10月7日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について開始決定が出ました。
令和6年10月19日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について再生計画認可決定確定が出ました。
令和6年9月3日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和6年9月6日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和6年9月10日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について再生計画認可決定確定が出ました。
令和6年9月3日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。
令和6年9月3日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和6年9月19日に名古屋地方裁判所にて再生手続開始事件 について再生計画認可決定が出ました。
令和6年9月25日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。
令和6年9月30日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について個人再生委員選任決定が出ました。
令和6年9月30日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて再生手続開始事件 について申立てました。
令和6年8月9日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について決定が出ました。
令和6年8月9日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和6年8月9日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について申立てました。
令和6年8月16日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。
令和6年8月16日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について申立てました。
令和6年8月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について申立てました。
令和6年8月29日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。
令和6年8月28日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。
令和6年7月18日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について再生計画認可決定が出ました。
令和6年7月22日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和6年7月26日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について決定が出ました。
令和6年7月26日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和6年6月3日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について申立てました。
令和6年6月11日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件について決定が出ました。
令和6年6月14日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について開始決定が出ました。
令和6年6月24日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について開始決定が出ました。
令和6年6月18日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。
令和6年6月18日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について破産手続廃止決定が出ました。
令和6年6月26日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。
令和6年5月8日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について申立てました。
令和6年5月9日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続き開始決定が出ました。
令和6年5月9日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続き開始決定が出ました。
令和6年5月13日に名古屋簡易裁判所にて不当利得返還請求事件 について民事訴訟を提起しました。
令和6年5月14日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和6年5月14日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。
令和6年5月15日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について再生計画認可決定確定が出ました。
令和6年5月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について決定が出ました。
令和6年5月14日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。
令和6年5月20日に名古屋地方裁判所一宮支部にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和6年5月29日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続きが終結しました。
令和6年5月28日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。
令和6年4月30日に名古屋地方裁判所岡崎支部に再生手続開始事件 について申立てました。
令和6年4月25日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について申立てました。
令和6年4月25日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について申立てました。
令和6年4月23日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について破産手続きが終結しました。
令和6年4月18日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について申立てました。
令和6年4月17日に名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件 について開始決定が出ました。
令和6年4月15日に名古屋地方裁判所に再生手続開始事件 について再生計画認可決定が出ました。
令和年4月12日に岐阜家庭裁判所に不動産・債権仮差押命令申立事件についての担保取消決定が出ました。
令和6年4月3日に名古屋裁判所豊橋支部に再生手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和6年3月1日に名古屋地方裁判所豊橋支部で破産手続開始事件について破産手続廃止決定が出ました。
令和6年3月6日に名古屋地方裁判所で破産手続開始事件について個人再生委員選任決定が出ました。
令和6年3月11日に名古屋地方裁判所岡崎支部で破産手続開始事件について開始決定が出ました。
令和6年3月19日に名古屋地方裁判所岡崎支部で破産手続開始事件について破産手続きが終結しました。
令和6年3月19日に名古屋地方裁判所岡崎支部で破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。
令和6年3月25日に名古屋地方裁判所で破産手続開始事件について申立てました。
令和6年3月25日に名古屋地方裁判所で破産手続開始事件について申立てました。
令和6年3月26日に名古屋地方裁判所で破産手続開始事件について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。
令和6年3月22日に名古屋地方裁判所一宮支部で破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。
令和6年2月6日に名古屋地方裁判所で小規模個人再生事件について開始決定が出ました。
令和6年2月15日に名古屋地方裁判所一宮支部で破産手続開始事件について申立てました。
令和6年1月10日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。
令和6年1月11日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について開始決定が出ました。
令和6年1月17日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。
令和6年1月18日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。
令和6年1月25日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について申立てました。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
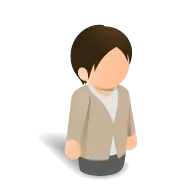
Aさん 30代女性 の場合
Aさんは、3社以上の複数社から300万円以上の借入れをしていましたが、一部の会社への支払いを滞納し訴訟予告通知を受けており、弊所へ債務整理のご相談にいらっしゃいました。
| 借金 |
|---|
| 消費者金融会社 3社 300万円以上 |
| 合計 300万円以上 |
Aさんから詳しくお話を伺い、Aさんの手元には多少まとまった金額の預貯金があるものの、とある事情により、一部の会社への支払いが滞納になっているということが分かりました。
そこで、Aさんと相談のうえ、借入金額の低い会社へは一括返済し、3社と任意整理をするということで弊所にて受任いたしました。
担当弁護士より、3社に分割払いの和解提案をし、それぞれおおよそ60回の分割払い・将来利息免除の和解を締結することができました。
本件では、Aさんは返済原資をお持ちであったため、借入金額の低い会社については一括返済することとしました。
任意整理のメリットは、月々の支払金額を減らせること、利息を減額できること等にありますが、借入金額の低い金融機関との任意整理は、あまり効果的でないこともありますので、どのように任意整理を行うかを検討する必要があります。
また、破産や個人再生といった法的手続との比較も必要になります。法的手続においては債権者を平等に取り扱う必要がありますので、方針が定まらないうちに行動を起こすと問題になることもありますので注意が必要です。
債務整理をお考えであれば、一度弁護士にご相談ください。
個人事業主の方から、営業自体は黒字になっている等の理由で、事業を継続したまま破産をして債務を整理することができないかという相談を受けることがあります。
しかし、個人事業を継続しながら破産をすることは困難なことが多いです。本稿では、その理由について述べます。
破産者が個人事業主の場合、同時廃止事件ではなく、管財事件になることが一般的です。本稿執筆時現在、名古屋地方裁判所においては、破産者が申立前5年以内に個人事業を行っていた場合は、原則として管財事件とする運用になっています。
管財事件として破産手続が開始されると、破産手続開始決定時の財産・負債を基準とし、財産は管財人によって換価され、負債については破産債権として他の借り入れ等と同様に取り扱われます。また、双方未履行の契約については、管財業務に不要と判断されれば、管財人が契約を解除します(破産法53条1項)。
そうしますと、個人事業主の場合、事業の継続という観点から主に以下の3点の問題が生じます。
個人事業主の場合、差押禁止財産に該当する場合を除いては、その財産が事業用かどうかにかかわらず、原則として管財人によって換価されます。
事業用の財産を残すことができる場合として考えられるのは、当該財産に財産的価値がなく、換価されずに財団から放棄される場合や、親族などの援助を受けて管財人から買い受ける場合等です。
破産手続開始決定前の原因による債務は、破産債権として他の債権と平等に取り扱われることとなります。財産を換価し余剰が出た場合には配当がなされますが、債権全額には及びません。
そのため、支払いを継続することができず、事業の継続は困難になってしまいます。また、支払いを受けられなかった取引先からの信用が失われてしまうことも考えられます。
このような事態を避けるためには、親族などから援助を受けるか、取引先に事情を説明して取引を継続してもらうようにお願いする等の対応が必要になりますが、いずれにしても実現は容易ではないと思われます。
破産管財人は、管財業務に不要な契約関係については、解除して整理していきます。そうすると、事業を継続する上で必要な契約についても、管財業務に不要と判断されれば解除されてしまうことになります。そのため、契約を続行するためには管財人の了承が必要になります。
したがって、破産手続中も個人事業を継続するためには、これらの問題をクリアしなければならないということになります。しかし、援助してくれる親族などがいる場合でも、破産を決断するまでには既に援助を受けている場合もありますし、援助の金額にも限界があります。また、取引先が取引を継続してくれるかどうかは取引先の判断に委ねられているので、手を尽くせば解決できるという性質のものでもありません。
また、破産した後は信用情報機関へ信用情報が登録されるため、基本的に新規の借り入れはできなくなりますので、借り入れをせずに資金繰りをしていく必要もあります。
このように、現在の個人事業を継続しながら破産することは困難であるといえます。したがって、個人事業を継続しながら債務を整理したい場合には、まずは任意整理や、個人再生手続の利用を検討することがよいでしょう。もっとも、いずれも継続的な支払いを前提にするものですから、本当に事業を継続して返済・履行をすることができるのかについては、しっかりと検討する必要があります。
破産以外の方法が選択できないという場合は、一度安定した収入を得られる形で就労する等して破産し、破産手続が終了した後に再度一から個人事業を開始するという方法も考えられます。ただし、過去7年以内に免責許可決定を得ていることは免責不許可事由の一つであり(破産法252条1項10号イ)、破産をしたとしても、再度の免責許可が得られない可能性がある点には注意が必要です。
債務整理手続を検討する際には、様々な点を考慮しなければなりません。弊所では、個人事業主の方も含め、個人の方からの債務整理の相談をお受けしていますので、債務整理をお考えの方は、一度ご相談ください。
個人再生や破産等の債務整理を行う際、多数の資料(家計の状況、陳述書等)を収集、作成のうえ、裁判所へ提出(申立て)することになります。資料の収集には、最低でも2か月程度かかるため、申立てをするまでにかなりの労力が必要です。
しかし、個人再生の場合、申立てをした後にも、非常に重要な手続きがあります。今回は、そのなかの1つである「積立金(履行テスト)」についてご説明いたします。
個人再生は、裁判所へ必要資料の提出(申立て)をしてから、認可決定(申立人の個人再生を裁判所が認める決定)がなされるまで、平均で6か月程度かかります。個人再生では、基本的に36カ月(3年)以内で圧縮された債務を申立人が弁済する必要があります。
裁判所は、申立人が提出した資料を検討し、申立人が本当に弁済できるのかを判断します。仮に、裁判所が申立人による3年以内の弁済ができないのではないかと考えた場合、個人再生の申立てが認められないおそれがあります。
そうすると、申立人は、裁判所に対し、債務の弁済を継続して行うことができる旨を丁寧に説明する必要があります。そこで、重要となるのが「積立金(履行テスト)」です。
履行テストとは、毎月、弁護士口座か申立人自身の口座へ、一定額を積み立てていくことをいいます。例えば、再生計画案に毎月4万円を債権者へ弁済する旨を記載のうえ、裁判所へ提出したとします。この場合、申立てから認可決定がなされるまでの数か月の間、毎月4万円以上を積み立てていくことができれば、裁判所に対し、現状4万円以上の積立が毎月できているので、将来的にも毎月4万円の弁済が可能である旨を説得的に説明することができます。
つまり、履行テストは、将来の弁済が可能であることを裁判所へ説明する根拠になるため、非常に重要ということです。履行テストが上手くいけば、それだけ裁判所が申立人の個人再生を認める可能性が高くなります。
逆に、履行テストが上手くいかない場合(例えば、月4万円の弁済を計画しているにもかかわらず、月3万円以下の積立金しかない等)、裁判所としては、本当に弁済できるのか疑念を抱くことになると思います。
履行テストでは、毎月の弁済計画額よりも、プラス1万円以上の積立てをする方が安心です。仮に、弁済計画額よりも多くの金額を積み立てることができていれば、その差額は貯蓄していることになります。そうすると、将来的に不測の支出があった場合でも、その貯蓄から補うことができるといえるため、より将来的な弁済が継続して行える可能性が高いといえます。
履行テストでは、毎月一定額を積み立てることが重要となります。なぜなら、弁済は毎月一定額を債務者へ支払うことになるからです。例えば、賞与をすべて積立てしたとしても、将来的に継続して弁済できることの根拠とはならないため、あまり意味がないです。
個人再生の認可決定がなされるか否かは、裁判所へ申立てを行ってからの数か月が非常に重要となります。履行テストが上手くいけば、それだけ個人再生が認められる可能性が高まるため、毎月一定額の積み立てをお願いいたします。
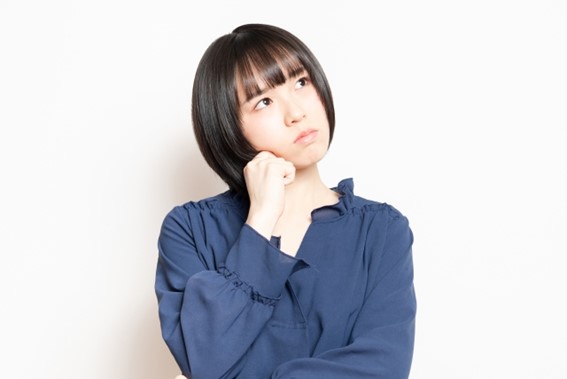
民事再生手続とは、裁判所において、債務者の債務を弁済する計画を立てる手続です。債務を減免し、また期間に猶予をもたせて、定期的に弁済する計画を立てます。
個人再生手続は、民事再生手続のうちのひとつで、債務者が個人である場合に適用できる手続です。通常の民事再生手続よりも簡易な手続である点が特徴です。
個人再生手続には、小規模個人再生と、給与所得者等再生の2つがあります。
⑴ 利用のための要件
小規模個人再生は、①将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること、②再生債権(再生債務者(再生手続をする人)に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権)の総額が5000万円を超えないことが利用の条件になります。①の要件は、給与所得者であれば満たされると考えられますし、個人事業主であっても、少なくとも3か月に1回の割合で債務を弁済する原資となる収入を得られる見込みがあれば満たされると考えられます。
⑵ 弁済額
小規模個人再生において再生手続を経て弁済することになる額は、以下のとおりです。
小規模個人再生においては、原則、3年で債務を弁済する計画を立てるので、100万円を3年で弁済できる資力、つまり毎月約3万円は支払えるだけの余裕がある人でなければ利用することは難しいです。
しかし、上記の金額よりも、清算価値(その債務者が破産した場合、債権者が得られる仮定的な破産配当)の方が高ければ、その清算価値が弁済することになる額になります。
⑶ 債権者の決議
小規模個人再生においては、再生計画について、債権者の決議を経ることが必要です。再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないときに、再生計画案の可決があったものとみなされます。したがって、債権者のうちの過半数が計画に同意しない旨の回答をした場合や、特定の債権者が債権総額の半分を超える債権を有しており、その債権者が再生計画案に同意しない旨の回答をした場合は、再生計画は可決されません。
⑴ 利用のための要件
給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則で、小規模個人再生の手続を選択できる債務者のうち、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」が選択できます。額の変動の幅は、年収額の5分の1程度が目安と解されています。
⑵ 弁済額
給与所得者等再生において再生手続を経て弁済することになる額は、可処分所得の2年分です。可処分所得とは、わかりやすく言うと、収入から所得税や社会保険料に相当する額と債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な費用を引いた額です。
可処分所得の2年分は、たいてい、小規模個人再生で弁済することになる額よりも高額になります。したがって、給与所得者等再生を選択できる人でも、小規模個人再生を選択する人がほとんどです。
⑶ 債権者の決議
給与所得者等再生においては、債権者の決議がいらないという大きな特徴があります。ときどき、会社の方針で、再生計画には常に反対する債権者がいますが、そのような債権者が過半数の議決権を有していると、小規模個人再生において再生計画案が可決されないことになります。その場合は、給与所得者等再生を選択することの検討が必要になります。
以上のように、小規模個人再生にも給与所得者等再生にも一長一短があります。
個人再生手続は債務が減り、生活が楽になるように思えますが、計画どおりに定期的に債務を弁済しなければならなくなるため、申立準備中はもちろん、手続中、手続終了後も、家計簿をつけ家計を把握することや、節制することが必要になります。小規模個人再生にせよ、給与所得者等再生にせよ、債務から完全に開放される手続ではありません。その認識をもって、手続に臨むことが必要です。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
| 平日 | 9:00-18:30 |
|---|---|
| 夜間 | 17:30-21:00 |
| 土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
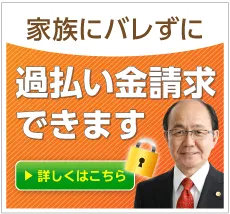
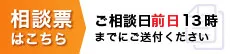
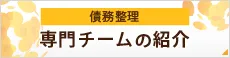
事務所外観




より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
【取り扱いエリア】
愛知県西部
(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部
(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部
(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部
(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部
(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部
(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)